兄弟との関係に悩み、「兄弟不仲の原因の1位は何?」と気になっている方は少なくありません。
子どもの頃は些細な喧嘩で済んでいた関係も、大人になってから溝が深まり、修復が難しくなるケースが多く見られます。
兄弟仲が悪いのは親の責任、親のせいと感じる人も多く、特に不公平な接し方が原因で生じた感情は、大人になっても消えにくいものです。
兄弟不仲の原因には、親の態度だけでなく、性格や価値観の違いなど、さまざまな要因が関係しています。
長年の確執から「仲が悪いから話さない」「付き合いをやめた」「絶縁した」といった状態に至ることも少なくありません。
本記事では、大人になってから兄弟仲が悪くなる理由や、兄弟不仲の根本原因、さらにはスピリチュアルな観点で語られるカルマの影響など、多角的に解説していきます。
今の関係を見直したい方、距離を取るべきか悩んでいる方にとって、考えるヒントになる内容をまとめました。
記事のポイント
- 兄弟不仲の原因1位は親からの不公平な扱い
- 大人になってから兄弟関係が悪化する理由
- 兄弟不仲に親の責任がある場合とない場合の違い
- 絶縁や付き合いをやめる判断の背景や心境
兄弟不仲の原因の1位は親の影響だった?
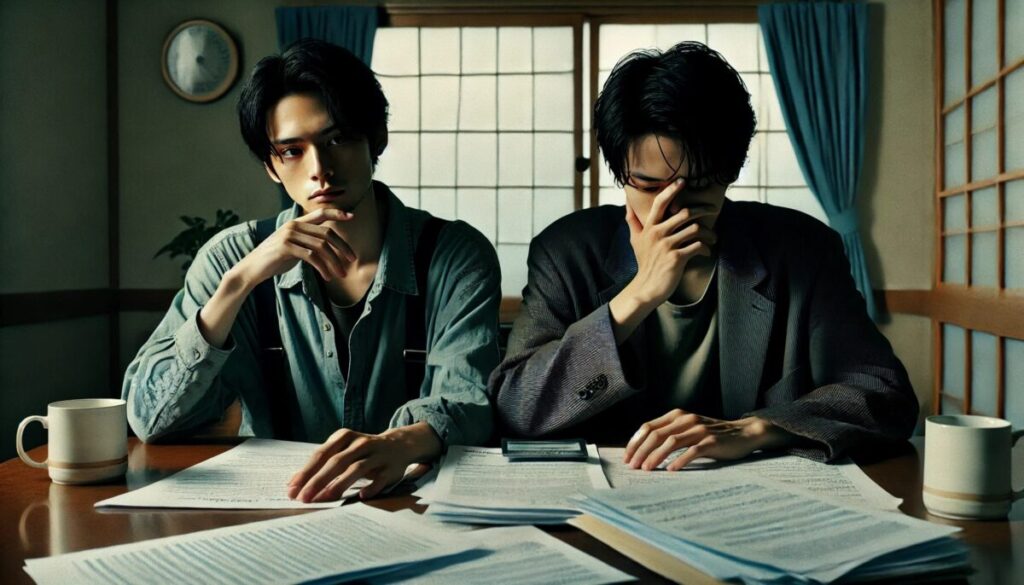
- 大人の兄弟が不仲になる要因1位とは?
- 兄弟仲が悪いのは親のせい?親の責任ではないケース
- 兄弟仲悪いことで大人になってから起きる問題
- 兄弟が仲が良い割合はどれくらい?
- 兄弟との付き合いをやめた人の心境
大人の兄弟が不仲になる要因1位とは?

大人になってから兄弟が不仲になる要因の中で、最も多く挙げられるのが「親からの不公平な扱いによる確執」です。
子どもの頃は無意識に受け流していた感情であっても、時間が経ち、社会経験を積んだ大人になったときに、過去の記憶がより鮮明になり、不満や怒りとして表面化することが珍しくありません。
例えば、親が兄だけを頼りにしていた、妹ばかりを可愛がっていたといった経験があると、それぞれの心に「自分は認められていなかった」「愛されなかった」という思いが深く刻まれます。
このような感情は、普段は心の奥に沈んでいても、親の介護問題や財産相続といったシビアな問題を前にすると、一気に噴き出してしまいます。
さらに、大人になればなるほど、兄弟間で歩んできた人生の違いも明確になります。
経済状況や家庭環境、親への関わり方などがズレる中で、「自分だけが負担を背負わされている」と感じる場面が出てくるのです。
このとき、子ども時代の不公平感と結びつき、不信感や憎しみが強まってしまう傾向にあります。
ただし、親の態度だけが原因というわけではありません。
兄弟それぞれの感じ方や性格、置かれた状況も影響しています。
たとえ親が平等に接していたつもりでも、受け取り方によって「不平等」と感じることもあるため、単純に親を責めるだけでは根本的な解決には至りません。
これを防ぐためには、まず兄弟一人ひとりが「過去にとらわれすぎないこと」が重要です。
また、親に対して過剰な期待を抱かず、自分自身の人生に責任を持つ覚悟も必要になります。
そして、兄弟と接する際には、無理に距離を縮めようとするのではなく、適度な距離感を保ちつつ、必要なときには冷静にコミュニケーションを取る姿勢が求められるでしょう。
いずれにしても、兄弟との関係は一朝一夕で変わるものではありません。
感情的になりすぎず、少しずつでも信頼を積み上げていくことが、大人同士の関係を修復する上での第一歩となるのです。
兄弟仲が悪いのは親のせい?親の責任ではないケース

兄弟仲が悪くなる原因として「親の育て方」が指摘されることは多いですが、必ずしも親の責任だけとは限りません。
実際には、親とは無関係な要素で兄弟同士の関係が悪化するケースも少なくないのです。
例えば、大人になるにつれてそれぞれの価値観やライフスタイルが大きく異なるようになった場合です。
兄は堅実に会社員として働き、弟は自由な生き方を選んだといったように、人生観の違いが広がると、互いに相手を理解できず、距離が生まれることがあります。
この場合、親がどれだけ平等に接していても、兄弟間の摩擦は避けられないこともあるでしょう。
また、経済的格差も兄弟関係に影響を与えることがあります。
たとえば、一方が成功し、もう一方が経済的に苦しい状況に置かれていると、嫉妬心や劣等感が関係に影を落とすことがあります。
このような感情は、親の育て方よりも、その後の社会的な環境や本人の選択によるものが大きく影響していると考えられます。
さらに、兄弟それぞれの性格やコミュニケーション能力の差も無視できません。
例えば、もともと感情を表に出すのが苦手な兄と、感情的に衝突しやすい弟がいる場合、どちらが悪いというわけではなく、単純に性格の相性が悪いだけということもあるのです。
このように、兄弟仲が悪い原因にはさまざまな背景が存在します。
もちろん、親の影響がゼロではない場合もありますが、「すべて親のせい」と決めつけるのは適切ではありません。
自分自身や兄弟それぞれの立場や選択を冷静に見つめ直すことが、より健全な関係を築くための第一歩となるでしょう。
兄弟仲悪いことで大人になってから起きる問題
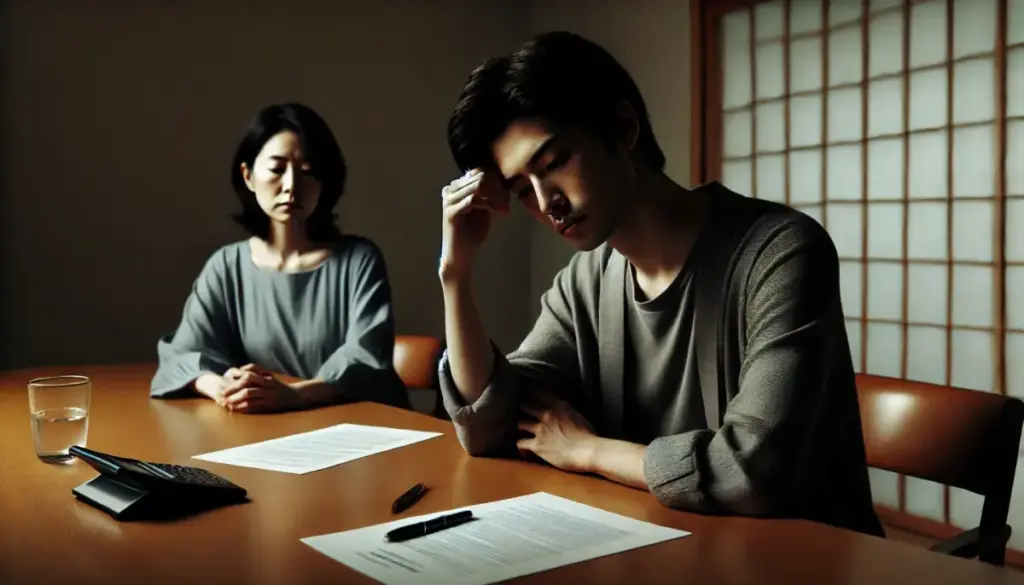
大人になってから兄弟仲が悪いと、避けて通れない現実的な問題が次第に表面化してきます。
その中でも特に多いのが「親の介護」や「遺産相続」をめぐる対立です。
これらは感情面だけでなく、金銭的・時間的な負担も大きいため、もともとの関係があまり良くなかった兄弟ほど深刻なトラブルへと発展しやすくなります。
たとえば、厚生労働省の「介護保険事業状況報告」によれば、令和6年7月末時点で65歳以上の第1号被保険者数は約3590万人、そのうち要支援・要介護認定を受けている人は約704万人に上ります。
これは65歳以上のおよそ5人に1人が介護を必要としている計算になります。
こうした中で「誰が介護するのか」「費用はどう分担するのか」といった問題が生じたとき、兄弟仲が良くなければ建設的な話し合いが難しくなります。
感情的な対立を避けられず、連絡すら取らなくなるケースも少なくありません。
また、家庭を持ったことで価値観が変わり、お互いにとって理解し合えない存在になっていることもあります。
親の医療方針や施設選びなどを巡って意見がぶつかり、たとえその問題が解決しても、わだかまりだけが残ることもあります。
こうした状況の根底には、幼少期から築かれてきた信頼関係の希薄さがあることも多いです。
昔から「話が合わない」と感じていた兄弟同士では、どちらかが歩み寄る努力をしなくなり、関係修復の糸口さえ見失ってしまいます。
さらに、仕事や家庭に追われる日々の中で、兄弟間のコミュニケーションが極端に減るのも問題です。
連絡を取る機会が少なくなることで、すれ違いは解消されず、そのまま関係が冷え切ってしまうことも珍しくありません。
このように、大人になってからの兄弟関係は、放置すればするほど修復が難しくなる傾向があります。
可能であれば、できるだけ早い段階で冷静な話し合いや連携の機会を持つことが大切です。
兄弟が仲が良い割合はどれくらい?

株式会社NEXERと株式会社ニーズ・プラスの「兄弟間の親密度に関する調査」では、兄弟姉妹と「仲が良い」と答えた人の割合は70.4%という結果が出ています。
これは、子どもの頃から一緒に過ごす時間が長いことで、自然に信頼関係が築かれる傾向があるためと考えられます。
例えば、幼少期に同じ空間で遊んだり、学校行事や家庭内の出来事を共有した経験が多い兄弟は、大人になっても連絡を取り合う習慣が残りやすく、困ったときに助け合う関係を続けているケースもあります。
家族行事や親のサポートといった機会も、絆を深める一因として挙げられるでしょう。
一方で、約3割の人は「仲が悪い」や「ほとんど交流がない」と回答しています。
こうした関係の背景には、性格の不一致や生活環境の違い、過去のトラブルなどが関係していることが少なくありません。
たとえ血のつながりがあっても、自動的に良好な関係が築けるわけではないという現実があります。
この調査結果からは、兄弟との関係が良好かどうかは、育った環境だけでなく、互いの努力や価値観の共有が影響していることが読み取れます。
親密な関係を維持している兄弟には、お互いに適度な距離感を保ちつつ、必要なときには支え合う姿勢が見られるのです。
したがって、現在兄弟との関係に悩みを感じている場合でも、必ずしも70.4%の「仲が良い」という数値に引け目を感じる必要はありません。
それぞれの兄弟関係には個別の事情があるため、無理に理想的な形を目指すよりも、自分たちにとって心地よい距離感や関わり方を見つけていくことが大切です。
兄弟との付き合いをやめた人の心境

兄弟との付き合いをやめた人の心境は、単なる怒りや憎しみだけでは説明できないものがあります。
むしろ、長い葛藤の末に「これ以上関わることは自分にとって良くない」と判断した結果、距離を置く選択に至るケースが多いのです。
例えば、何度も同じことで裏切られたり、価値観の違いから話すたびにストレスを感じる場合、人は自然と「これ以上傷つきたくない」と考えるようになります。
このように言うと冷たい決断に思えるかもしれませんが、自分の心を守るためには必要な選択であることも少なくありません。
また、付き合いをやめた後に後悔を感じる人もいれば、「もっと早く距離を取ればよかった」と安堵する人もいます。
どちらにしても、兄弟との関係に無理をし続けるより、自分らしく生きることを重視した結果であることが多いのです。
このため、兄弟との付き合いをやめる決断は、軽いものではなく、多くの葛藤と自己理解を経た末のものといえるでしょう。
兄弟不仲の原因の1位は親の死後に表面化する

- 親の死による兄弟関係への影響
- 葬式で起こる兄弟間トラブルとは
- 仲悪い兄弟と話さない状態でも問題ない?
- 兄弟との絶縁を選ぶタイミングとは
- 関係を修復したい場合の具体的な方法
- 兄弟仲が悪いことのカルマやスピリチュアル的視点
親の死による兄弟関係への影響

親の死は、兄弟関係に大きな影響を及ぼします。
それまで親を介して保たれていた兄弟間の連絡や繋がりが、親の死をきっかけに一気に薄れることが少なくないからです。
特に、親が健在だった頃は「親のために顔を合わせる」という目的があったものの、それが失われると、自然と兄弟同士の距離も開きやすくなります。
例えば、葬儀や遺産分割の場で意見が対立すると、そこから深刻な不仲に発展するケースもあります。
誰がどのように親の介護に貢献したか、相続において公平だったかどうかなど、感情的な争いに発展する要素が多いためです。
一方で、親の死をきっかけに兄弟が絆を深める場合もあります。
共に悲しみを乗り越える過程で、改めてお互いを理解し合うことができるからです。
ただし、このような良い関係を築くためには、普段からある程度の信頼関係を維持しておくことが不可欠です。
このため、親の死後に兄弟仲を悪化させないためには、元気なうちから親を交えた話し合いや、兄弟間でのコミュニケーションを大切にしておくことが重要だといえます。
葬式で起こる兄弟間トラブルとは

葬式の場は、兄弟間のトラブルが起きやすいタイミングの一つです。
普段は距離を置いていた兄弟同士が、突然重要な判断を迫られるため、意見の食い違いや感情的な衝突が表面化しやすくなります。
例えば、葬儀の形式や規模について意見が割れたり、費用負担をめぐって揉めることがよくあります。
誰がどれだけ費用を出すべきか、どのような手順で進めるかについて考え方が異なれば、話し合いはすぐに難航してしまいます。
また、親の介護にかかわった度合いや、生前の親との関係性が原因で、不満や恨みが噴き出す場合もあります。
このとき、過去のわだかまりが一気に表面化し、収拾がつかなくなることも少なくありません。
このようなトラブルを防ぐためには、親が元気なうちに、葬儀に関する希望や費用分担についてあらかじめ兄弟間で話し合っておくことが効果的です。
突然の場面で感情的にならないよう、できるだけ事前に準備しておくことが、後悔のない葬儀に繋がります。
仲悪い兄弟と話さない状態でも問題ない?

仲が悪い兄弟と話さない状態を続けることに、大きな問題がないケースもあります。
無理に関係を修復しようとしてストレスを感じるくらいなら、一定の距離を保ったほうがお互いにとって良い場合もあるためです。
例えば、過去のトラブルが深刻で、話し合いを試みても改善が見込めない場合には、無理に接触を持たないほうが心の健康を守れます。
このように考えると、話さない選択は一種の自己防衛とも言えるでしょう。
ただし、親の介護や相続など、避けられない場面で協力が必要になることもあります。
そのときに最低限のコミュニケーションが取れないと、トラブルが大きくなりやすいため、全く連絡を絶つのではなく、連絡手段だけは確保しておくのが現実的です。
いずれにしても、仲悪い兄弟と無理に仲直りを目指す必要はありませんが、必要な場面で最低限の対応ができる関係性は維持しておくほうが後悔が少なく済みます。
兄弟との絶縁を選ぶタイミングとは

兄弟との絶縁を選ぶタイミングは、人によって異なりますが、一般的には「もう関係を続けることで自分が壊れそうだ」と感じたときが一つの目安になります。
例えば、暴言や金銭トラブルなど、何度注意しても改善が見られない場合には、これ以上関わること自体が大きなリスクになります。
このとき、単に距離を置くのではなく、明確に「絶縁」という形を取ることで、自分の生活や精神的な安定を守ることができるのです。
他にも、親の介護や遺産相続をめぐってあまりに深刻な対立が起こり、関係修復が不可能だと判断した場合も、絶縁のタイミングとして選ばれることがあります。
このような場合、感情的な勢いで絶縁を宣言するのではなく、冷静に状況を見極めたうえで判断することが重要です。
つまり、絶縁は最後の手段であり、自分の人生を守るためにやむを得ない選択として行われるべきものだと考えられます。
関係を修復したい場合の具体的な方法

兄弟との関係を修復したいと考えたとき、大切なのは「関係を改善したい」という意思を明確に持ち、その意志を相手に伝えることです。
ただし、急に歩み寄ろうとしても相手に警戒されることがあるため、段階的なアプローチが必要です。
まず試してほしいのが、小さな会話のきっかけを作ることです。
たとえば、親の健康状態や家族行事について連絡を入れることで、自然な形でやり取りを始めることができます。
いきなり感情的な話題を避け、あくまで情報共有から入るのがポイントです。
次に意識したいのが、過去の対立やわだかまりに固執しない姿勢です。
謝罪が必要であれば簡潔に気持ちを伝えることも重要ですが、相手を責める言い方は避けましょう。
「あのときは自分も未熟だった」といった、自己開示を含む表現が相手の心を開く手助けになります。
また、距離を縮めるには無理をしない関係性の構築が欠かせません。
仲直り=頻繁な交流ではなく、お互いがストレスを感じずに関われる関係を目指すべきです。
数ヶ月に一度のメッセージ交換や、年に一度の顔合わせなど、少しずつ関係を温めていくようにしましょう。
さらに、第三者を通して距離を縮める方法も有効です。
共通の知人や親、親戚などを介して話を伝えてもらうことで、直接のやり取りよりも気持ちが伝わりやすくなることがあります。
いずれにしても、兄弟関係の修復には時間がかかることも珍しくありません。
焦らず、相手の反応を見ながら一歩ずつ前進することが、長期的な関係改善への近道となるでしょう。
兄弟仲が悪いことのカルマやスピリチュアル的視点

兄弟仲が悪い理由をスピリチュアルな観点から見ると、「カルマの影響」が関係していると考えられることがあります。
カルマとは、前世から引き継がれる魂の課題や因果応報を意味し、現世での人間関係にも影響を及ぼすとされています。
つまり、兄弟として生まれたのは偶然ではなく、お互いに学び合うための必然だったという考え方です。
例えば、前世で解消できなかった対立やわだかまりを、現世で兄弟という近しい関係の中で乗り越えるべき課題として持ち越している場合があります。
このとき、表面的には些細なことで衝突していても、実際には魂の深い部分で影響を受けている可能性があるのです。
一方で、スピリチュアルな考え方を取り入れることに抵抗を感じる人もいるでしょう。
現実的な視点で見れば、性格の不一致や育った環境の違いといった要素も、兄弟仲に大きく作用しているからです。
このため、カルマの影響だけに原因を求めるのではなく、目の前の具体的な関係性にも目を向けることが重要です。
このように、兄弟仲の悪さをスピリチュアルな視点から理解しようとすることは、自分たちの関係性を見つめ直すきっかけにはなり得ますが、あくまで一つの考え方としてバランスよく捉える必要があります。
兄弟不仲の原因の1位の実態と影響まとめ
記事のポイントをまとめます。
- 親の不公平な扱いが兄弟間に確執を生む
- 子どもの頃の感情が大人になってから表面化する
- 介護や相続を機に過去の不満が噴き出す
- 「愛されなかった」という思いが深い傷になる
- 経済状況や家庭環境の違いが不信感を強める
- 親の態度が平等でも受け取り方に差がある
- 自分と兄弟を比べることが関係悪化を招く
- 親の死後に兄弟間の距離が一気に広がる
- 遺産分割や葬儀準備でトラブルが起きやすい
- 大人になると価値観の違いが関係を分断する
- 経済格差が嫉妬や劣等感を生みやすい
- 性格の不一致が長期的な不仲の要因になる
- スピリチュアルな視点ではカルマが影響するとの見方もある
- 無理に関係修復を目指さず適度な距離を保つことも選択肢
- 絶縁を選ぶのは心身を守るための最終手段となることがある

