新入社員が仕事中に寝てしまうという場面は、職場で誰しも悩ましい問題です。
仕事中に寝てしまう原因には、環境の変化による疲労や不規則な生活習慣だけでなく、モチベーションの低下や眠気を引き起こす病気が潜んでいる可能性もあります。
また、仕事中寝てる人に対しては、イライラする社員も少なくないでしょう。
適切に注意しつつ、ただ叱責するだけではなく、居眠りの背景にある心理に寄り添うことが大切です。
この記事では、仕事中に寝る新人の居眠りへの注意の仕方や、クビのリスクに至る前に行える対策を紹介します。
さらに、寝る人の心理や新入社員の居眠りを注意してもパワハラにならないか、居眠りがひどい人を支援する方法についても詳しく解説します。
仕事中寝ている人へのイライラを解消しながら、職場全体のパフォーマンスを維持するための具体的な対応策をご紹介します。
記事のポイント
- 新人が仕事中に居眠りする心理や原因
- 居眠りする新人への適切な注意とパワハラ回避法
- 新人の居眠りが職場に与えるリスク
- 居眠りの改善がない場合の病気の可能性
仕事中に寝る新人が抱える問題

- 寝る人の心理とは
- 仕事中に寝てしまう原因と背景
- 寝てしまうのは病気のせい?
- 居眠りが引き起こすリスクとは
寝る人の心理とは

新人が仕事中に居眠りをしてしまうのには、いくつかの心理的背景があります。特に、環境の変化や業務への慣れが原因となることが多いです。
まず、新しい職場に入ったばかりの新人は、環境の変化による緊張やストレスで体力が消耗しやすくなります。
仕事の覚えるべきことが多く、初めての社会人生活に適応しようとする中で、肉体的・精神的に疲労が蓄積されやすく、眠気につながることがあります。
また、自己管理がまだ不十分な場合、生活リズムが安定せず、睡眠不足が重なることもあるでしょう。
さらに、仕事中に居眠りをしてしまうもう一つの心理的背景として、モチベーションの低下が考えられます。
新人がまだ業務に楽しさややりがいを見出せていない場合、集中力が欠け、無意識に眠気を感じてしまうこともあります。
特に、単調な作業が続くと、業務に対するモチベーションが低下し、集中力が途切れやすくなります。
このような状況で眠気を感じるのは、心理的な負担が影響していると言えるでしょう。
このように、新人が居眠りをしてしまうのには、環境適応へのストレスや業務に対するモチベーションが大きく関わっています。
心理的な要因が関係しているため、上司や先輩が理解を持ってサポートすることも重要です。
仕事中に寝てしまう原因と背景
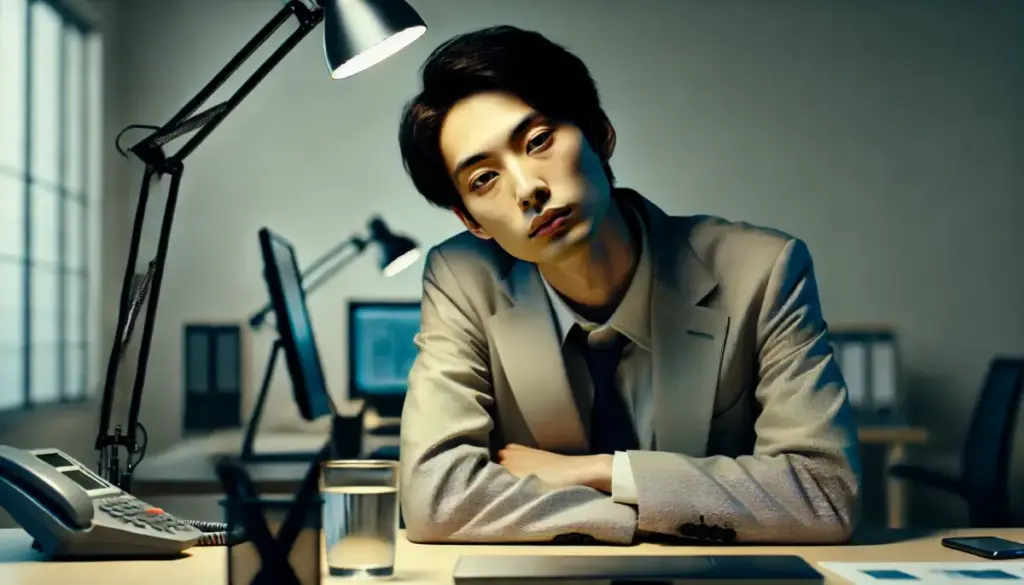
仕事中に眠くなる原因には、いくつかの要因が考えられます。
単に睡眠不足だけでなく、生活習慣や職場環境、体調の状態などが複雑に絡んでいます。
一つ目の原因として、睡眠の質が低いことが挙げられます。
特に若い世代では、スマートフォンやパソコンを夜遅くまで使用しているため、ブルーライトの影響で体内時計が乱れやすくなっています。
これにより、夜間の睡眠が浅くなり、翌日の仕事中に強い眠気を感じることがあります。
社会人としての生活リズムが身についていない新人にとって、この影響は大きいでしょう。
また、職場環境も眠気に影響します。
会議が長時間にわたり、内容が単調だったり、空気の流れが悪い部屋での業務では、酸素不足が原因で眠気が生じやすくなります。
特に、暖房が強く効いている室内では体温が上昇し、リラックス状態に近づくため、眠気が促進されることがあります。
さらに、疲労やストレスも無視できない要因です。
特に新人は、新しい環境での仕事や人間関係に適応するため、無意識のうちにストレスがかかり、体力が消耗しやすくなっています。
この状態では、脳がリラックスを求めて眠気を引き起こしやすくなります。
こうした原因から、仕事中に眠気を感じるのは、睡眠の質や職場環境、そして日々の疲労やストレスが複合的に作用している結果です。
寝てしまうのは病気のせい?

仕事中の居眠りがあまりにも頻繁で改善が見られない場合、もしかすると病気が関係している可能性もあります。
慢性的な眠気や、十分に睡眠を取ったにもかかわらず日中に強い眠気に襲われる場合は、ただの疲労ではなく睡眠障害を疑うことが大切です。
代表的な病気には「睡眠時無呼吸症候群」や「ナルコレプシー」などがあります。
まず、「睡眠時無呼吸症候群」は、睡眠中に何度も無呼吸の状態が起き、睡眠が断続的に中断されることで、質の良い眠りが得られない状態です。
十分な睡眠時間を確保しても、呼吸が止まることで睡眠が浅くなり、日中に強い眠気を感じやすくなります。
この状態では、本人が無意識のうちに睡眠不足のような状態になり、昼間の居眠りが増える可能性があります。
睡眠時無呼吸症候群は、重度の場合、生活習慣病のリスクを高めるだけでなく、仕事中の集中力を低下させる要因にもなるため、治療が必要です。
次に、「ナルコレプシー」という病気も考えられます。
ナルコレプシーは、日中に突然強い眠気に襲われる病気で、意識に反して急に眠りに落ちてしまうことが特徴です。
仕事中でも急な睡眠発作が起こり得るため、本人の意思ではコントロールできない場合があります。
この症状があると、どれだけ努力しても仕事中に居眠りを防ぐことが難しくなり、業務や人間関係に支障が出ることもあります。
ナルコレプシーも、専門医の診断と治療を受けることで、薬などを活用しながら症状のコントロールが可能です。
以上のように、居眠りが単なる疲労や生活習慣の問題でない場合には、これらの病気が関係している可能性があります。
長期的に症状が改善されない場合や、他の対策が効果を感じられない場合には、早めに医師の診断を受け、必要な治療を行うことが大切です。
居眠りが引き起こすリスクとは

新入社員が仕事中に居眠りをしてしまうことは、企業や職場環境にいくつかのリスクをもたらします。
具体的には、業務効率の低下、周囲の社員への悪影響、そして新人自身の評価やキャリアに対する悪影響が考えられます。
まず、居眠りによって新入社員の業務効率が低下します。
居眠りをしている間は当然ながら業務が進まず、仕事に必要な情報や指示を取りこぼしてしまう可能性もあります。
こうした小さなミスが積み重なると、業務全体に遅れが出るだけでなく、同僚や上司にフォローを依頼する事態に陥ることも考えられます。
また、仕事の遅れや手戻りが増えれば、新人が自ら抱えるストレスも増大し、さらに居眠りが増える悪循環に陥る可能性もあります。
次に、居眠りをしている新人がいると、職場全体の士気に影響が出ることがあります。
特に、他の社員が真剣に業務に取り組んでいる中で新人が居眠りをしている姿を見ると、「仕事に対する意識が低いのではないか」といった不信感を招きやすくなります。
これにより、周囲の社員が不快感を感じたり、職場の一体感が損なわれたりすることが考えられます。
職場環境の雰囲気が悪化すると、新人だけでなく他の社員の生産性も低下してしまう可能性があるため、周囲への影響は見過ごせないポイントです。
また、新人自身の評価にも大きなリスクが伴います。
居眠りの頻発は、業務に対する意欲が低いとみなされ、信頼を失う原因になりかねません。
特に、業務中の居眠りが注意されても改善が見られない場合には、「自己管理ができていない」「社会人としての意識が不足している」と評価され、将来のキャリアにも影響を及ぼす可能性があります。
悪い印象が定着すると、昇進や昇給の機会に不利となるだけでなく、今後の成長機会を逃す結果になることも考えられます。
このように、新入社員の居眠りは個人の評価やキャリア、そして職場全体の雰囲気にさまざまなリスクをもたらします。
そのため、居眠りが頻発する場合は、早い段階で適切な対策を講じることが望ましいと言えるでしょう。
仕事中に寝る新人への適切な対応

- 居眠りがひどい人に対する対策
- 居眠りする人への注意の仕方
- 新入社員の居眠りを注意したらパワハラ?
- 仕事中寝てる人にイライラしないための工夫
- 改善されない場合はクビにした方がいい?
居眠りがひどい人に対する対策

居眠りがひどく、繰り返し起こる新人に対しては、効果的な対策を講じることが重要です。
まず、新人がなぜ居眠りをしてしまうのか、その原因を把握することが第一歩です。
原因が不明なまま指摘を繰り返しても、根本的な解決にはつながりません。
生活リズムの乱れや過労が理由であれば、体調や環境の整備を促すことで改善が期待できます。
また、業務が高度すぎて負担になっている場合には、仕事の量や内容を再評価し、段階的に成長を促すことも有効です。
具体的な対策として、まず新人の生活リズムや健康管理の意識を高めることが挙げられます。
例えば、日常の睡眠時間の確保や、リフレッシュのための時間を設けるようにアドバイスすることで、疲労を軽減できる可能性があります。
また、業務中の眠気対策として、ガムを噛んだり、こまめに席を立つなど、眠気を防ぐ具体的な行動を推奨するのも効果的です。
さらに、職場環境の改善も対策のひとつです。
デスク周りの換気を良くし、適切な室温を保つことで、眠気が起こりにくい環境を作り出せます。
酸素不足や温度が高すぎると集中力が低下し、眠気につながりやすいため、周囲の環境に目を配ることも大切です。
場合によっては、休憩時間を効果的に活用するように提案し、15分ほどの仮眠を取ることも対策として有効です。
最後に、本人と上司、もしくは先輩が一緒に解決策を考える場を設けるのも良い方法です。
居眠りの問題を個人だけの責任にするのではなく、サポートする姿勢を見せることで、新人も安心して対策に取り組めるようになります。
このように、個々の事情や職場環境に合わせた柔軟な対応が、居眠りの問題を解消し、新人のパフォーマンス向上につながるでしょう。
居眠りする人への注意の仕方

新人が仕事中に居眠りをする場面に対して、どのように注意をするかは非常に重要です。
適切な注意の仕方をしないと、新人がやる気を失ってしまったり、逆に不信感を抱いてしまうこともあります。
まずは、状況に応じた冷静で建設的な指摘が大切です。
新人への注意は、まず事実を確認することから始めましょう。
居眠りが頻繁であれば、なぜそのような状況が続いているのか、原因に理解を示す姿勢を見せることが求められます。
例えば、業務内容が難しく感じているのか、生活リズムが安定していないのかを丁寧に聞き出し、本人が抱えている課題を見つける姿勢が重要です。
このように原因を共有することで、新人もただの叱責として受け取らず、自分の問題として考えやすくなります。
注意をするときには、周囲に人が少ない静かな環境で行うことが望ましいでしょう。
周りに人が多い状況で指摘すると、居眠りをしてしまった新人が不必要に恥をかいたり、気まずさを感じたりしてしまいます。
そのため、他の人に知られないように個別に呼び出し、静かに話をすることで、冷静かつ効果的に伝えられるでしょう。
また、指摘の仕方としては、まず「あなたに期待している」「頑張っていることは理解している」といった前置きを伝えると、相手のモチベーションを下げずに話を進められます。
そして、その後で具体的に「最近、仕事中に眠気を感じることが多いようですが、大丈夫ですか?」と問いかけることで、指摘が柔らかく受け取られやすくなります。
このアプローチによって、新人が自分の行動を見直すきっかけになりやすくなります。
加えて、居眠りの対策方法についても一緒に考える姿勢を見せることがポイントです。
例えば、昼食後の眠気対策として体を動かす、少し冷たい水で顔を洗うなど、対処法を一緒に考えましょう。
こうすることで、新人も自分に合った対策を実践しやすくなり、上司や先輩との信頼関係も深まります。
新入社員の居眠りを注意したらパワハラ?

新入社員の居眠りに対して注意をする場合、「パワハラになるのでは?」と心配になることがあるかもしれません。
しかし、適切な方法で指導を行えば、パワハラには該当しません。
ここでは、パワハラを避けつつ、新入社員の居眠りを注意する際のポイントを解説します。
まず、パワハラとされる行為とは、上司が部下に対して必要以上の叱責を行ったり、人格否定や不当な扱いをしたりすることです。
具体的には、「お前はダメなやつだ」「やる気がないなら辞めてしまえ」といった侮辱的な発言や、一方的に責め立てる行動が該当します。
そのため、居眠りを注意する場合も、こうした言葉遣いや過度な叱責には細心の注意が必要です。
一方で、業務の一環として居眠りを指摘し、業務上の改善を促す行為は適切な指導であり、パワハラとは異なります。
ポイントは、居眠りについて「どう改善するか」を主体に話を進めることです。
例えば、「午後の会議で居眠りが目立っていたが、どんな理由があったのか?」と、まず状況を確認する質問を投げかけるとよいでしょう。
その上で、「もし業務に対する疲労が原因であれば、休憩を挟むタイミングを見直すことも大事です」と、実際の対策を共有することが重要です。
さらに、注意する際には、冷静なトーンで事実に基づいた説明を行い、相手の視点も尊重する姿勢を持つことが求められます。
たとえば、「最近の居眠りでミスが増えているため、業務の進行に影響が出ている。この点について一緒に改善策を考えたい」と、業務の影響を示しつつ建設的なアプローチを心がけると、パワハラと見なされにくくなります。
最後に、もし居眠りが頻繁で改善が見られない場合でも、短期間で即断しないことが大切です。
居眠りの背景には、業務への不安や適応に時間がかかっている可能性もあるため、一定の成長を見守る姿勢が重要です。
こうした冷静で協力的な姿勢で接することで、指導がパワハラに誤解されるリスクを最小限に抑えることができます。
仕事中寝てる人にイライラしないための工夫
仕事中に新人が居眠りをしている場面に直面すると、上司や同僚としてはどうしてもイライラする気持ちが湧いてしまうかもしれません。
しかし、その感情が職場全体の雰囲気や新人の成長に悪影響を与えないよう、冷静で建設的な対応を心がけることが重要です。
イライラを和らげ、効果的にサポートするための工夫をいくつか紹介します。
まず、新人が居眠りをしてしまう背景や理由を冷静に理解することが重要です。
新人にとって、慣れない環境での仕事や新しい業務は思った以上に心身に負担がかかりやすいものです。
特に、職場の緊張感や指導のプレッシャー、仕事への不慣れが相まって、本人の意識とは裏腹に疲れがたまり、居眠りにつながってしまうことがあります。
こうした背景を理解しておくと、「何度言っても治らない」という一方的な見方ではなく、「どうすれば新人の業務に対する集中力や体調が改善できるか」といったサポートの視点を持つことができるでしょう。
このように、背景を考えるだけでも、イライラが和らぎ、新人に対して寛容な目を向けやすくなります。
次に、イライラの感情をポジティブな視点に変える工夫も効果的です。
例えば、居眠りが続く原因として、新人の生活リズムや体調管理がうまくできていないことも考えられます。
これを新人の成長の一環として捉え、「体調管理の重要性も仕事の一部」として、アドバイスや指導を行うことで、相手も受け入れやすくなり、こちらも前向きな気持ちで接することができます。
こうした視点を持つことで、新人を支援し、励ますような対応ができるようになります。
また、具体的な対策を導入しておくことも有効です。
新人にとってわかりやすい業務スケジュールを提供したり、短い休憩を挟むことでリフレッシュを促したりすると、集中力の維持が期待できます。
さらに、業務の合間に声かけをして、体調や不安について相談しやすい環境を整えるのも良い手段です。
新人が「自分の意見や不安を聞いてくれる」と感じれば、信頼関係が築かれ、体調不良やストレスが表面化しやすくなります。
このように、構造的にサポートすることで、居眠りの原因に対する具体的なアプローチができるでしょう。
最後に、自分自身の心のゆとりを持つ方法も取り入れると良いでしょう。
新人の行動に対して自分が感情的になっていると感じた場合、深呼吸をして気持ちを落ち着かせたり、業務に集中することで、感情のコントロールを図ります。
こうすることで、職場の雰囲気が悪化せず、結果的に新人もリラックスして業務に取り組むことができます。
以上の工夫を通じて、新人の居眠りに対するイライラを抑えつつ、より建設的なサポートが可能になります。
感情に流されず、落ち着いた態度で接することが、新人の成長を見守り、職場全体の雰囲気を維持するためのポイントです。
改善されない場合はクビにした方がいい?

新人が職場での居眠りを何度も繰り返し、改善の兆しが見られない場合、上司や同僚から「業務に支障が出るなら、解雇もやむを得ないのでは?」と感じることがあるかもしれません。
しかし、居眠りの問題が即「クビ」という極端な対応につながるわけではありません。
解雇という手段は最後の手段であり、それに至る前に検討すべき対応や手順があります。
まず、居眠りが続く背景には、新人が職場に適応しきれていない場合や、体調面や環境要因が関係している可能性があります。
緊張やストレス、または不規則な生活リズムが原因で慢性的な睡眠不足に陥っている場合、新人社員が意図せず居眠りをしてしまうことも少なくありません。
こうした場合、仕事に慣れていく中で改善する可能性もあるため、短期間で判断を下すのは避けるべきです。
また、業務の指導方法や作業環境を見直すことで、パフォーマンスが上向くケースも多く見られます。
次に、居眠りが続く新人社員に対しては、まず口頭での注意や改善を促す面談などを行うことが基本です。
業務に支障をきたしていることを具体的に伝え、なぜ居眠りが起こってしまうのか、新人の意見を聞きながら原因を探ることが求められます。
例えば、「睡眠不足が続いている」「業務中に集中力が保てない」など具体的な原因が見つかれば、解決策を一緒に考える機会にもなります。
また、場合によっては職場の配置転換やタスクの調整を検討することで、居眠りが改善される可能性もあります。
しかし、すべての対応を行った上で、なお居眠りが改善されず、業務の妨げとなり続ける場合は、上司や人事部門と協議のうえ、最終的な判断をする必要があります。
クビにするという判断は、業務に対するやむを得ない措置として慎重に行われるべきです。
その際には、当人が納得できる形での説明や、解雇前に改善のための指導やサポートを実施した記録も必要になります。
結論として、新人の居眠りが続く場合、すぐに「クビにした方がいい」と結論を出すのではなく、適切な指導やサポートを通して改善の余地を見つけることが大切です。
業務改善の可能性を探る努力を惜しまず、そのうえでどうしても解決できない場合にのみ、解雇も一つの選択肢として考えるようにすることが望ましい対応です。
仕事中に寝る新人が抱える問題と対策まとめ
記事のポイントをまとめます。
- 新人が仕事中に居眠りする原因には、緊張やストレスが影響する
- 睡眠不足や生活リズムの乱れが眠気を引き起こしやすい
- 職場環境の温度や酸素不足も眠気の要因になる
- モチベーションが低いと集中力が低下し、眠気が強まる
- 居眠りは業務効率の低下を招きやすい
- 居眠りが職場全体の士気を下げる要因となる
- 新人の評価やキャリアに悪影響を及ぼすリスクがある
- 睡眠障害の可能性がある場合は医師の診断が必要
- 睡眠時無呼吸症候群やナルコレプシーが原因の可能性もある
- 健康管理の意識を高め、生活リズムを整えることが効果的
- 職場環境を改善し、眠気が生じにくい空間を作るとよい
- 注意は冷静で建設的に行うことでパワハラを防ぐ
- 注意の際には新人に対する期待や理解を伝えるとよい
- 一緒に対策を考えることで新人のモチベーションを高めやすい
- 解雇は最終手段であり、指導とサポートを優先する

